
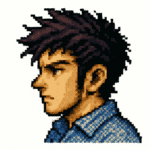
もうすぐでゴールデンウィーク。大型連休のご予定を立てられている方も多いと思います。これまでの私は、連休を与えられても、あまり有効活用ができず、気付けばもうお休みは終わっていて、なんだか休んだ感じがしない・・・!という経験を何度もしてきました。また休みに入ってからその準備に充てる日があるとすれば、それはもったいない。休日は休日にフルベットできるよう、そういった状況は今回をもって、断ち切りたい。
もうすぐでゴールデンウィーク。心身をリフレッシュする絶好の機会のはずなのに、休み明けに「結局あまり休めた気がしない…」と感じたことはないでしょうか?実際、有職者男女を対象にした調査では、正月休み明けに6割以上が何らかの「疲れ」を感じていたことが報告されています。せっかく休んだはずなのに疲労感が残っている——これは残念でなりません。
なぜ長期休暇を取っても十分に休んだ実感が湧かないのでしょうか?原因の一つには、休みに入る前の過ごし方が関係しています。休暇に入る前の段取りや心構え次第で、休暇中のリフレッシュ効果が大きく左右されるのです。心理学に詳しいメンタリストのDaiGoさんやサイエンスライターの鈴木祐さんも「休みに入る直前の準備」がカギだと指摘します。例えば、休暇前にあらかじめ計画を立てたり、仕事モードからオフモードへ切り替える儀式を行ったりすることで、休暇を最大限充実させられるというのです。
しかし一方で、「休みまでガチガチに計画したら本末転倒では?」「きっちり段取りを組むのは逆にストレスになりそう…」という声も聞こえてきます。実際、心理学の研究でも余暇の予定を詰め込みすぎると楽しみが減ってしまうことが示されています。では、計画的に準備するのと、ゆるく構えるのと、どちらが正解なのでしょうか?
本記事では、休暇前の準備戦略を構築します。「休みに入る前の最小限で効果的な準備の段取り」とは何かを探り、最後に今日から実践できる3つのシンプルな準備ルールも紹介します。それでは、休暇を真に「休んだ!」と言えるものに変えるヒントを見ていきましょう。

「休んだ気がしない」を生むものは何か?
まず最初に、長期休暇を取ったのにリフレッシュした気分になれない理由を考えてみます。「しっかり休んだはずなのに疲れが残る」「休み明けに憂鬱になる」という現象には、いくつか心当たりがあるでしょう。
- 仕事のことが頭から離れない: 休暇中もつい仕事の進捗やメールが気になってしまい、心が休まらない。
- 予定を詰め込みすぎている: 旅行やイベントのスケジュールをびっしり入れすぎて、かえって疲れてしまう。
- 何もしなさすぎて後悔する: 「せっかくの休みをムダにしたのでは…」と感じてしまい、休んだ充実感が得られない。
これらは多くの人が経験することでしょう。実際、連休明けに仕事へ行くのが憂鬱な理由として、「連休中に出かけたりしてかえって疲れたから」「生活リズムが崩れて体がだるいから」といった声が上位を占めます。要するに、休暇中の過ごし方によっては心身の疲労が十分に取れなかったり、新たなストレスを生んでしまったりするのです。
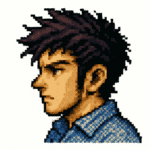
私含め、上記3点に当てはまる方は、意外に多いのではと思います。
「何もしなさすぎて後悔する」が、一番厄介。。
大型連休に入るまでに、事前対策を一緒に講じていきましょう。
では、どうすれば「休んだ気がしない」事態を防げるのでしょうか?ポイントは休みの始まりをどう迎えるかにあります。休暇の効果を最大化するには、休みに入る前から適切な準備を行い、仕事モードからオフモードへのスムーズな切替えを図ることが重要です。ここからは、心理学・行動科学に基づいた休暇前準備の戦略を見ていきましょう。
休暇前「計画と儀式」で最高のリフレッシュを
休暇の過ごし方として大事なのは、休みが始まる前の段階で意識的な準備をすることです。具体的には、「計画を立てる」「オンからオフへの切替え儀式を行う」「非日常的なチャレンジを取り入れる」といった戦略が挙げられます。それぞれの狙いと効果を、心理学・行動科学のエビデンスとともに見ていきましょう。
1. 休暇の計画を立てて“予測の幸福”を味方に
長期休暇に入る前にあらかじめ計画を立てておくことは、実は休暇の満足度を高める上で大きなメリットがあります。心理学の研究によれば、楽しいイベントを計画して待ち望む段階で人の幸福感は高まることがわかっています。オランダで行われたある調査では、休暇に出かける前の8週間もの間、旅行の計画を立てている時期に幸福度が高まったという結果が報告されています。つまり、休暇そのものだけでなく、「もうすぐ休みが来る!」とワクワクしながら準備する時間こそが大きな喜びをもたらすのです。
計画を立てることで、休暇中に「何をしようかな?」と悩む時間が減り、心に余裕が生まれます。また、あらかじめ楽しみの種を仕込んでおくことで、「あれもやりたかったのに休みが終わってしまった…」という後悔を防ぐこともできます。実際、科学的な時間管理術の観点からも「前もって休暇の予定を立てる」ことは推奨されています。仕事が立て込んでいると休暇取得自体を先送りしがちですが、数ヶ月前から旅行やイベントの計画を入れておけば、「その日に向けて頑張ろう」という前向きなモチベーションにもつながります。
ただし、計画はあくまでガイドラインです。後述するように、予定を詰め込みすぎると本末転倒になりかねません。鈴木祐さんも著書やブログで、計画を立てる際は「余白」を残すことの大切さを強調しています。緻密な計画と程よいゆるさ――そのバランスが肝心だという視点は、後ほどハイブリッド戦略の部分で詳しく述べます。
2. 「仕事脳」から「休暇脳」へスイッチを切り替える儀式
休暇に入っても頭が仕事から離れない…この状態を防ぐには、明確なオン・オフの切替えが必要です。休みに入る直前に小さな“儀式”を行うこと。これは心理的なスイッチを切り替える合図になります。
例えば、仕事最終日の終わりに5分だけ時間を取り、デスクの整理や未完了タスクの洗い出しを行うのはおすすめです。明日以降に回す作業を書き出し、「ここまでやった!」と自分に区切りをつけることで、脳が仕事を保留しやすくなります。頭の中に残った「やり残し」は人の注意を引き続けてしまいますが、紙に書き出して計画を立てれば頭から追い出すことができます(この効果はツァイガルニク効果への一種の対処法と言えるでしょう)。
次に、オフモードに入る合図となる行動を一つ決めます。仕事が終わったら職場を出て15分散歩する、帰宅後すぐシャワーを浴びる、お気に入りの音楽をかける、アロマを焚く…なんでも構いません。「これをやったら休暇開始!」という自分だけのルーティンを作るのです。「切替えルーティン」の効果をしばしば説いており、人間の脳は環境や行動の変化によってモードを切り替えやすくなるといいます。スーツを脱いで部屋着に着替えるだけでも、「休みモード」に移行するシグナルになります。
さらに、物理的にも仕事の痕跡を遮断する工夫も効果的です。週末や休暇中は、仕事用PCや書類は目につかない場所に片付けましょう。スマホも仕事用の通知はオフに設定します。「仕事の連絡が来ると見てしまう」という人は思い切ってメールアプリをログアウトしたり、機内モードにしてしまってもいいでしょう。実際、心理カウンセラーは「休日は仕事に関するものを視界に入れず、メール通知も切ること」を勧めています。環境から仕事の手がかりを排除することで、脳も安心して休暇モードに切り替わります。
こうしたオフへの移行儀式を行うと、休み始めの最初の一日二日でだいぶリラックスできるようになります。研究によれば、人間は休みに入ってから1~2日経ってようやく仕事のことを忘れ始める傾向があるといいます。逆に言えば、最初の切替えがスムーズだと休暇全体の質が上がるのです。「オンからオフへのスイッチ」を意識して入れることで、せっかくの休みを最初からエンジン全開で楽しめるようになるでしょう。
以上、休暇前の「計画」「切替え儀式」の2つを紹介しました。では次に、こうした戦略への注意点も見てみましょう。「計画立てすぎは逆効果では?」「休みなんだから何もしないほうがいいのでは?」という疑問に、科学的視点から答えていきます。
計画過剰の落とし穴と“何もしない”という戦略
どんな戦略にもメリットとデメリットがあります。休暇前に入念に準備をする戦術にも、「やりすぎるとかえって疲れる」「義務感を生んでしまう」といった落とし穴が指摘されています。この章では、計画過剰による弊害と、あえて無計画・ノープランで過ごすことの効用について考えてみましょう。
予定を詰め込みすぎると楽しみが減る? 科学が示す意外な事実
スケジュール帳にぎっしり予定を書き込み、「この時間からこの活動」と休暇をカッチリ管理するのは、一見充実した休みに思えます。しかし心理学の実験は、レジャーに細かく予定を設定するとその楽しさが損なわれると示唆しています。
ワシントン大学などの研究によれば、レジャー活動に特定の日時を割り当ててスケジュール化すると、そのイベントが仕事の延長のように感じられてしまい、本来得られるはずの楽しみやワクワク感が減少してしまったそうです。計13件におよぶ実験で一貫して確認されたのは、「〇月〇日〇時に○○をする」ときっちり決めた場合、やっている最中でさえも「〜しなくては」と義務的な感覚が生じ、楽しみが薄れてしまうという現象でした。例えば友人とカフェで会う約束も、日時をかっちり決めた途端に「予定」の一つとなり、「行かなきゃ」と感じてしまう——研究者自身もそんな経験をし、この現象を科学的に調べたといいます。これは驚きですが、思い当たる節もあるのではないでしょうか。
つまり、休暇を有効に使おうとするあまり予定を詰め込みすぎると、本来の自由さが失われてストレスになる恐れがあるのです。せっかく立てた計画が、皮肉にも自分を縛る「ノルマ」や「締め切り」になってしまっては本末転倒ですよね。
「何もしない贅沢」の効用:ゆるく過ごすことで得られるもの
一方で、「せっかくの休みなんだから何も予定を入れずにのんびり過ごしたい」という人もいるでしょう。その直感は決して間違いではありません。近年注目されているオランダ発のリラックス法に「ニクセン(Niksen)」というものがあります。ニクセンとはオランダ語で「何もしない」を意味し、意図的にぼーっと過ごす時間を生活に取り入れる手法です。このニクセンが今、ストレス解消や創造性の向上に効果的だとして欧米で脚光を浴びています。
「何もしないなんて時間のムダでは?」と思うかもしれません。しかし専門家によれば、敢えて自分に「何もしない」ことを許すと、心身が義務感や生産性の呪縛から解放されて深くリラックスでき、結果的にストレスホルモンが減少するそうです。実際、忙しい日常で常に張り詰めていた神経が緩み、疲労や燃え尽き(バーンアウト)の予防になることが報告されています。さらに「何もしない時間」に人の脳はデフォルトモードネットワークが働いて、ふとしたひらめきが生まれやすくなるとも言われます。シャワー中や散歩中に良いアイデアが浮かぶ経験は誰にでもあるでしょうが、まさにあれは脳がオフ状態の時に起きる現象です。
日本人はとかく「何もしない」ことに罪悪感を抱きがちです。しかし、休暇中の適度な怠け時間は決して悪いものではなく、むしろ休息の質を高めてくれる大切なスパイスです。実際、あるアンケートで連休明けに憂鬱にならない人の過ごし方を調べたところ、「頭を慣らすためにぼーっとする時間を作った」と回答した人が少なからずいました。何もせずぼんやりすることで、心身に溜まった疲労がじんわり癒やされていく感覚を大事にしたいですね。
以上のように、「休み前に計画と準備をする派」と「休みくらい無計画に過ごす派」の双方に一理あることがわかります。計画を立てれば充実感が増す半面、詰め込みすぎると逆効果。ゆるく構えればストレスが減る半面、何も決めないと時間を持て余す危険もあります。結局、大切なのはバランスです。では最後に、それらを踏まえたハイブリッド型の休暇準備戦略を提案しましょう。

解決策:計画とゆるさの“いいとこ取り”!ハイブリッド休暇戦略
ここまで見てきたように、長期休暇を最大限にリフレッシュするには「ある程度の計画性」と「適度なゆとり」の両方が鍵となります。そこで提案したいのが、両者の良い部分を統合したハイブリッド型の休暇準備戦略です。以下に、休みに入る前に押さえておきたい最小限のオフ切替えチェックリストをまとめました。
最小限のオフ切替えチェックリスト:休暇前にこれだけは!
- 仕事の断捨離と“オフ宣言”: 休みに入る前日までに仕事のケリをつけましょう。未完了のタスクはリスト化して上司や同僚に引き継ぎを依頼し、「ここまでで休暇に入ります!」と周囲にも宣言します。最後の出社日の退勤時にはデスクを片付け、メールの自動応答(不在通知)を設定し、仕事用PCや書類は視界から消しておきます。こうすることで、自分にも他人にも「もう休みに入った」という明確な線引きをします。
- オンからオフへのマイルーティン: 休暇開始の合図となる自分なりのルーティンを用意します。例えば、「最終出勤日の夜は少し高級なビールで乾杯する」「連休初日の朝はいつもより1時間長く寝て、ゆっくりコーヒーを淹れる」「旅行に出る前夜にお気に入りの音楽を聴きながら荷造りする」など、仕事の日とは明らかに違う行動でスイッチを切り替えます。小さな儀式で構いません。大切なのは「休みが始まった!」という実感を自分に与えることです。
- 休暇中の目玉を一つ決める(しかし時間は縛らない): 長期休暇で「これだけはやりたい!」という目玉イベントを1つ設定しましょう。旅行でも趣味でも家族サービスでも構いません。ポイントは、日付や時間帯はざっくり決めて詳細は縛りすぎないことです。たとえば「○日に日帰りドライブに行く」くらいのラフな計画に留め、出発時間や細かい行程は当日の気分で調整する余地を残しておきます。こうすることで、事前に楽しみを確保しつつも、縛られすぎない自由さをキープできます。
- 「何もしない日」も予定に入れる: アクティブに過ごす日がある一方で、あえて何の予定も入れない日を休暇中に設けましょう。最初から「○日は一日中フリー」と宣言しておくのです。その日は文字通りダラダラ過ごしても良し、当日の気分で散歩に出ても良し。ポイントは「何をしなくてもOKな日」と自分に許可を与えることです。そうすることで、他の日に思い切り遊んでも「あとで休めるから大丈夫」という安心感が生まれます。心にゆとりがあるほど、アクティブに過ごす時間もより充実するはずです。
以上がハイブリッド戦略のチェックリストです。要するに、最低限の計画とけじめだけ付けてあとは自由に楽しむ、というアプローチです。事前に種をまいておいた「楽しみ」(計画)のおかげで休暇の充実度は上がり、適度な「余白」を残したおかげで息苦しさのないリラックスも確保できるのです。
ポイントは、計画と即興のハーフ&ハーフであること。スケジュール帳とにらめっこするのではなく、「やりたいことリスト」を描きつつ、実行タイミングは気分に任せるくらいの柔軟さがちょうど良いバランスです。こうすれば、休み本来の自由な解放感と計画することの楽しさを両取りできます。
今すぐできる!休み前準備の3つのシンプルルール
最後に、この記事を読んだ今日から実践できる3つのシンプルな準備ルールをまとめます。次の長期休暇に限らず、週末や有給休暇にも応用できますので、ぜひお試しください。
- 「終わり」を宣言せよ – 休みに入る前の仕事最終日、必ず自分なりの区切りをつけてください。翌日のタスクリストを書き出し机を片付け、「今日はここまで!」と声に出すくらいの勢いで仕事モード終了宣言をしましょう。終わりを明確にするほど、翌日からの休みを心置きなく楽しめます。
- 休暇のハイライトを仕込め – 長期休暇中の一番の楽しみを事前に1つ決めてカレンダーに入れておきましょう。それを糧に頑張れますし、休暇の満足度もぐっと高まります。ただし詳細は詰め込みすぎず、当日の気分で調整できる余裕を残すのがコツです。事前に楽しみの種をまき、当日は自由に育てるイメージで!
- 「何もしない」を恐れない – 休みの日を充実させなきゃ…と焦る必要はありません。むしろ1日くらいは予定ゼロの日を作る勇気を持ちましょう。何もしない贅沢は心身の最高のご褒美です。その余白があるからこそ、他の日に思い切り遊んだり動いたりできるのです。「何もしなくてもOK」と自分に許可を与えることが、結果的に休暇全体の満足度を底上げします。
以上の3ルールを意識するだけでも、次の休暇の充実度は大きく変わるはずです。難しいテクニックは何もありません。大切なのはメリハリとマインドセット。「休む前にちょっと準備」を習慣にして、休暇上手になりましょう。
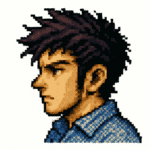
連休にやるといいことは、そういう本が出ていたりするので、項目としては分かりやすと思います。一方で、休みに入るまでに行っておくべきこと。この点を深掘りしているものはあまりなかったので、今日はこの点を徹底的に掘りまくりました。
休みに入ってから仕事のことが頭にあると、それだけでもったいない。
休みの期間中は、最大限に休みましょう!
おわりに:休み方次第で日常も変わる
「休むこと」にもスキルや戦略がある——少し大げさに聞こえるかもしれませんが、休暇の過ごし方を工夫するだけで日々の幸福感や仕事でのパフォーマンスまで変わってきます。実際、休暇でしっかり充電できれば、職場での挫折への耐性が増し、新たな解決策を見出すなど仕事に良い影響があることも研究で示されています。休暇をただの「何もしない時間」ではなく、「自分をリセットしアップデートする時間」として積極的に活用してみませんか?
最後に少し知的好奇心をくすぐる問いかけを。長い休暇を年に一度まとめて取るのと、短い休みを小まめに取るのでは、果たしてどちらが幸福度や効率に良いのでしょうか? 実はこの疑問には科学的な議論があり、興味深いデータも出始めています。
ではまた!
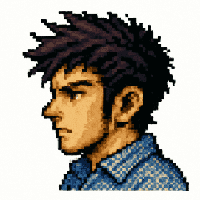

コメント