
面接や自己分析で「あなたの強みは何ですか?」と質問されたとき、何かモヤッと違和感を覚えた経験はないでしょうか。社会人ならこの問いに戸惑った経験がある方も多いはず。「強みなんて特にない…」と困ったり、無理にひねり出したりした方もいるはずです。それもそのはず、この問い自体に問題があります。「強み」は絶対的な能力ではなく、環境次第の相対評価に過ぎないからです。
要するに、能力の優劣は土俵次第で変わるということです。何が「強み」になるかも、置かれた環境や比較対象によって大きく異なります。言い換えれば、強みとはその組織や周囲の「弱み」の裏返しに他なりません。一つの能力も、比較対象や置かれた環境が変われば、強みにも弱みにもなり得るのです。
ではなぜ世間では「あなたの強みを伸ばそう」などとあたかも絶対的な長所が存在するかのように語られるのでしょうか。本記事では、そのパラドクスをひも解きながら、「勝てる場所で戦う」というキャリア戦略の重要性について考察します。ただし環境に頼るだけでは成長が止まるリスクもあるため、最後に環境選びと自己成長のバランスについて提言し、さらに自分の“勝てる場所”の見つけ方を具体的なチェックリストとして紹介します。「強みがない」と感じている方でもゼロから優位を築ける方法に触れ、記事の最後には明日から実践できる3つのアクションも提案します。
強みは職場で変わる?相対評価の不思議
職場で評価される「強み」は、実はその組織や周囲の人が持っていない要素である場合がほとんどです。裏を返せば、その場では当たり前に備わっている能力は強みになりません。同僚たちが皆できることを自分もできても「まあ普通だよね」で終わってしまいます。一方で周囲が苦手なことを自分ができれば「それは君の強みだね!」となるわけです。
たとえばある業界のコンサルタントとの対話で、「御社のサービスの強みは?」と尋ねたところ「礼儀正しさ」という答えが返ってきたケースがあったそうですnote.com。その業界では口の悪い応対が当たり前だったため、少し丁寧に対応するだけで顧客から高く評価されるとのことでした。しかし「礼儀正しさ」は銀行など別の業界ではごく当たり前すぎて強みにはなりません。要するに、礼儀正しさは「礼儀知らずが多い環境」でのみ強みになり得るということです。
このように強みとは相対的なものです。自分が属する組織やチームが何を不得手としているか、何を価値とみなしているかによって、評価は大きく変わります。逆に「強みがない」と感じている人も落ち込む必要はありません。強みは相対的なものなので、一般的に弱みでもそれを必要とする場を見つければ強みに化ける可能性があります。
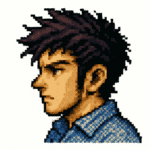
これから入ろうとしているところで、相対的な強みを聞くのって、実はなかなかな無理ゲーなんじゃね?と本当に思う。だってその環境、知らないから、他の方よりも優れているものなんて分からない。
加えて、仮にも出てきたその強みは、その職場とのニーズに合致するのかどうか。仮に建設会社へ面接に行ったとして、強みは「りんごの写真を見ただけで品種をバッチリ当てられます!」と言われても、言われた方も困るわけで。。。
「勝てる場所」で戦う—環境を選ぶキャリア戦略
自分の力を最大限に発揮するには、環境選びが極めて重要です。「どこで戦うか」を間違えると、本来の力も評価されません。裏を返せば、環境さえ選べば自分の力以上の成果を上げられることがあります。実際、ビジネスの世界でも「環境を味方につける者」のほうが「才能に頼る者」より成功しやすいという指摘がありますdiamond.jp。言い換えれば、能力そのものよりも発揮する場の方が勝敗を左右するということです。
「自分が勝てる場所で戦う」ことこそ賢い戦略です。自分が相対的優位に立てる土俵(「勝てる場所」)を選べば、あなたの強みは最大限に活きるのです。つまり、自分が相対的優位に立てるフィールドを選ぶことで強みが自然と際立ちます。

競争を避け続けることのリスク:成長機会の喪失
しかし、「勝てる場所」ばかり追い求めて競争から逃げ続けることにもリスクがあります。常に自分が優位に立てるぬるま湯に浸かっていると、挑戦する機会が減り成長が止まってしまいかねません。
実際、日本の社会人1200人を対象にしたある調査では、「ライバルがいる人」のほうが「ライバルが一度もいない人」よりも幸福度が高いという結果が報告されています。適度な競争や挑戦は人生にプラスの影響をもたらすのです。
また、今の強みも永遠ではありません。環境も競合も変化し続けるので、現状維持は後退とすら言えるでしょう。
要はバランスが大事です。環境を選ぶことで得られる相対的優位と、自らを鍛える成長への挑戦、この両輪を戦略的に回していきましょう。自分が勝ちやすい土俵では存分に力を発揮しつつ、ときにはあえて新しい土俵に踏み出してみる——そのバランス感覚が重要です。自分に合った適度なチャレンジを取り入れながら、着実に実力と実績を積み上げていくことを意識しましょう。

その「勝てる場所」をどう見つけていくのか?
では、自分にとっての「勝てる場所」とは具体的にどこなのでしょうか。それを見つけ出すための戦略をチェックリスト形式で紹介します。自分の適性や相対優位がまだはっきりしないという方も、以下のポイントを試してみることでヒントが得られるはずです。
- 自分の強み候補と周囲の弱みを探る: 自分が周囲より少しでも得意なことは何かを洗い出すとともに、職場で皆が苦手・敬遠しがちなことを観察してみましょう。両者が重なる領域こそがあなたの相対的な強みのヒントになります。
- 小さな実験を繰り返す: 自分の強み候補や勝てそうなフィールドについて仮説を立てたら、実際に試してみることが大切です。思い立ったら副業やボランティア、社内プロジェクトなどで小さくチャレンジしてみましょう。たとえ失敗してもうまくいかなくても、必ず得るものがあります。こうした実験を繰り返す中で、「これは手応えがある」という分野が見つかるはずです。
- スキルは「掛け算」でレアカード化へ:同じスキルを磨くだけでは競争激化に負けてしまいがちですが、2つ目を足すと一気に希少カード化します。
こうした試行錯誤で「ここなら勝てる!」というフィールドが見つかったら、あとはそこで努力を重ねましょう。その相対的な強みの芽はやがて研ぎ澄まされ、絶対的な武器へと成長していくはずです。
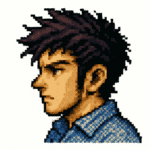
私の場合は幸いにも、現場監督したり作業したりするのが好きなメンバーの中にいるため、PCとか数字とか分析とかアウトプットが大の大の苦手な方々に囲まれていたため、ちょっと勉強しただけですごく重宝されました。
戦略的に見つけたわけではないですが、自分にとっては少し苦手な業界かな?と思っていたところに飛び込んだのは結果として良かったかなとも感じています。
ただ、重宝されたのはこの環境だからであって、そういった専門の方々の中に入って同じことをやろうものならば、全く役に立たないんだと思います。
勝てるところで戦うのは大事で、そういうところをどう見つけていけるか。楽に戦い続ける場所を見つけるスキルを磨くという視点もアリです。
明日からできる3つの行動
最後に、明日から実践できる小さなアクションを3つ紹介します。できるところから試してみてください。
- 強みを3つ書き出す: 人より得意だと思うことを3つ紙に書いてみましょう。自分の強みの再発見につながります。
- 他者に強みを聞く: 同僚や友人に「私の強みは何だと思う?」と聞いてみましょう。自分では気づかない意外な長所を教えてもらえるかもしれません。
- 新しいことに挑戦する: 普段やらない小さなチャレンジをあえて一つ実行してみましょう。たとえば職場で普段関わらない部署の仕事を手伝ってみる、社外の勉強会や副業にトライしてみるなど、いつもと違う環境に自分を置くことで相対的な得意・不得意が見えてきます。思わぬ強みの発見や人脈の拡大につながるかもしれません。
強み探しは一朝一夕にはいきませんが、「強みは絶対でなく相対的」と理解すれば肩の力もふっと抜けるはずです。人は環境次第で輝き方が変わるのです。根気強く自分が輝ける舞台を探し、見つけたらそこで腕を磨き続けてください。
ではまた!
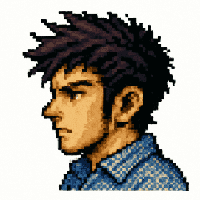








コメント