カウジです。昇格できなかったからこういう記事を書いているわけではありません(ほんとう)。
会社で昇格することは、能力や努力の結果として評価されるものと思われがち。しかし、20年もサラリーマンをやっていると、昇格は必ずしも有能な人が選ばれるわけではないという場面にうんざりするほど、出くわす。そして昇格は「無能を発見するためのゲーム」になっている側面もあって、その視点でみると、なかなか楽しい。
本記事では、サラリーマンの昇格が「無能発見ゲーム」になってしまう理由とその背景、解決策を解説します。
昇格が「無能発見ゲーム」になる理由
ピーターの法則と昇格の限界
「ピーターの法則」とは、「人は能力が認められて昇進を続け、最終的には無能になるまで昇進し続ける」という組織論です。例えば、優れた営業マンがマネージャーに昇格した途端、結果を出せなくなるケースがあります。
営業マンとしては優秀でも、管理職のスキルは別物。しかし、多くの企業はこの違いを理解せず、成果を出した社員を昇格させる。その結果、「無能な管理職」が生まれやすくなります。
「上司の評価」=「能力の評価」ではない
昇格の判断は上司の評価によります。しかし、上司も会社の政治的な駆け引きに関与しており、純粋な能力よりも「気に入られる力」や「都合のいい部下か」が重視されることがあります。
そのため、上司にとって扱いやすい人物が昇格し、組織のパフォーマンスが低下するケースが生じます。
有能な人が昇格を避けるケース
「本当に賢い人は無駄な出世を望まない」と考えます。
昇格すれば責任やストレスが増し、自由が奪われる。それならば、あえて出世を望まず、働きやすいポジションで成果を上げ続ける方が合理的だと考える人も多い。
この状況が続くと、昇格するのは「出世欲の強い人」ばかりになり、組織の質が下がります。
無能な管理職が増えると何が起こるのか?
無能な管理職が増えると、組織全体に以下の悪影響が生じる。
- 現場の士気低下:無能な上司に振り回され、優秀な社員ほど辞める。
- 意思決定の遅れ:判断力の欠如により、重要な決定が遅れる。
- 責任の押し付け合い:能力不足の管理職ほど部下に責任を押し付ける。
- 生産性の低下:無駄な会議や不適切な指示が増え、業務効率が悪化する。
これらの問題は、多くの日本企業で見られます。転職先も似たようなものだったという話は、たまーに聞きます。
「無能発見ゲーム」から抜け出す方法
「昇格=管理職」をやめ、「専門職コース」を設ける
海外企業では、「昇格=管理職」ではなく、「専門職コース」と「マネジメントコース」を分ける制度があります。日本企業でも、優秀なエンジニアや営業マンが無理に管理職になるのではなく、スペシャリストとして活躍できる仕組みを作るべきと考えます。
「管理職の適性」を重視した昇格制度
業績評価だけでなく、リーダーシップやマネジメント能力を客観的に評価する仕組みが必要だ。適性試験や研修を導入することで、「現場の有能さ」だけでなく「管理職としての適性」を見極めるべきである。
「上司の評価」ではなく「360度評価」を導入する
昇格の決定権を上司だけに委ねるのではなく、同僚や部下の評価も取り入れる「360度評価」を導入することで、本当に適性のある人材を昇格させられる。
「出世しない選択肢」を認める
昇格しないことが「負け組」とされる風潮を変え、各自のキャリアを尊重する文化が必要。「管理職にならなくても、会社に貢献できる仕組み」を整えれば、出世にこだわらない優秀な人材も活躍しやすくなります。
まとめ
サラリーマンの昇格が「無能発見ゲーム」になるのは、ピーターの法則や組織の評価システムの歪みが原因。有能な人ほど出世を避け、結果的に組織の生産性が低下する。
この問題を解決するには、「昇格=管理職」をやめて「専門職の道」を用意する。「360度評価」などの新しい評価制度を導入するなど、企業の仕組みを見直すことが不可欠。
個人としては、出世のメリット・デメリットを冷静に分析し、「自分にとって最適なキャリア」を選択することが重要だ。単に出世を目指すのではなく、長期的に自分の人生が豊かになる選択をすることが求められる。
そう考えると、私はだいぶ早い段階で無能判定が出たような気がします。
でもそれはそれで、違うことにチャレンジすればいいんだ(はーと)くらいの気持ちでいます。
ではまた!
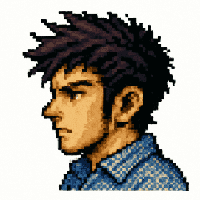








コメント